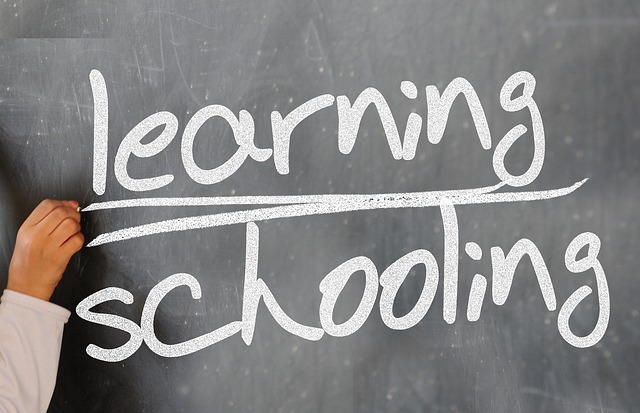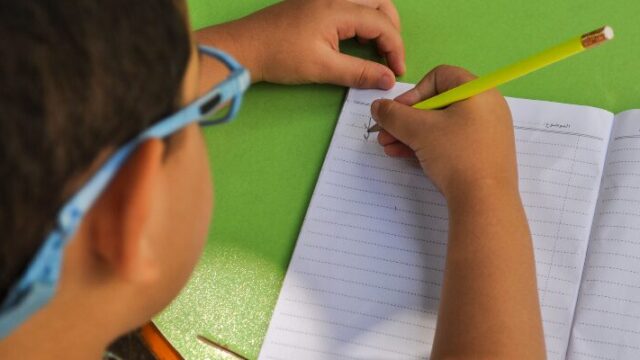- 「小学校入学、ちゃんとやっていけるかな?」
- 「授業についていける?」
- 「小学校生活、ちゃんと楽しめるかしら?」
わが子の成長が嬉しい反面、「何を準備すればいいの?」と不安に思う保護者はとても多いです。
私は現役小学校教員として、毎年多くの新1年生とその保護者を迎えてきました。そしてその後、子どもたちがどんな成長をし、どんな苦労をするのかをこの目で見てきました。
私自身も同じ悩みを抱えた一人の親として、これまで得た貴重な経験から、「これさえやっておけば安心!」という具体的な小学校入学に向けた準備を、我が子に実践してきました。
そこでこの記事では、我が子の小学校の入学に向けてどんな準備をすれば良いか明確になるよう、具体的な実践内容とその理由まで詳しく解説します。
小学校入学準備が必要な理由

小学校入学前の準備は、子どもの学校生活へのスムーズな適応と将来的な学力アップ、豊かな学校生活に向けて極めて重要です。
小学校では、幼稚園や保育園と異なり、学習内容や生活習慣に大きな変化があります。事前の準備をすることで、お子様は新しい環境に戸惑うことなく、安心して学校生活を送ることができます。
実際の教育現場で、入学前の準備が十分でない子どもたちは、小1プロブレムという問題に直面することが多いです。
小学校入学準備は単なる学習スキルの習得だけでなく、子どもの人生における重要な転換点を成功させるための戦略的な投資です。小学校入学準備をすることで、子どもは安心して新しい環境に適応し、学びや人間関係を前向きに楽しむことができます。無理のない範囲で、できることから始めていきましょう!
我が子に本気で身に付けさせた5つのこと


それでは、ここからは我が子の小学校入学に向け、本気で身につけさせようと取り組んだ5つのことを紹介していきます。結論からいうと以下の5つです。
- 1 ひらがな・カタカナ・数字の読み書き
- 2 たし算・ひき算のイメージ作り
- 3 1日5分机に向かう習慣
- 4 論理的な思考力
- 5 モリモリ食べる習慣
それぞれ詳しく紹介していきます。
1 ひらがな・カタカナ・数字の読み書き
小学校入学前にひらがな・カタカナ・数字の読み書きができるようになることで、学校での学習をスムーズに始められます。
入学時に基本的な文字や数字の読み書きができる子どもは、授業の理解度が格段に高くなります。


なんせ、すぐに始まる授業は文字を読みながら始まるわけですからね。
国立教育政策研究所の研究では、早期の文字学習が読解力と言語能力の発達に大きく貢献するというデータもあるようです。
これまで実際に見てきた子どもたちの中で、入学前にひらがなとカタカナをマスターしていた子どもたちには、こんな共通点がありました。
- ・新しい言葉を学ぶスピードが早く、国語の読み取りが得意になる
- ・文字の読み書きで疲弊することがない
- ・国語や算数など、理解できることが増え、テストの点が高い
- ・色々な本が読めるため、読書が好きになる
文字や数字の早期学習は、学校生活の基本となる重要なスキルです。小学校入学に向け、楽しみながら少しずつ覚えていくことが大切です。
2 たし算・ひき算のイメージ作り


たし算・ひき算の基本的な考え方を理解していると、小学校の算数がスムーズに学べます。
- 「1+1=2」「2+2=4」と覚えていて言える子
- 「1+1=2」「2+2=4」をイメージできている子
両者にはその後の算数を学んでいく上での大きな差があります。
小学校の算数は、最初に「ものの数を増やす・減らす」というたし算・ひき算の考え方から始まるので、小学校入学までに数の増減、たし算・ひき算のイメージ作りができていると、小学校算数へのハードルが一気に下がりますよ。
おやつが「3こ」あって、お母さんが「2こ」追加してくれたら全部で「5こ」。このような日常生活の中で、たし算・ひき算の感覚を自然に身につけることが大切です。数の増減を意識した声かけをすることで、入学後の算数の理解がスムーズになり、「勉強って楽しい!」「算数っておもしろい!」と感じやすくなります。
3 1日5分机に向かう習慣
毎日わずか5分でも机に向かう習慣は、学習への姿勢と集中力を育てます。
東京大学の発達心理学研究によると、幼少期からの継続的な学習習慣は、脳の前頭前野の発達を促進し、自己制御能力と学習意欲を高めることが分かっています。
最初は短い時間でも構いません。
・絵を描く
・迷路を解く
・簡単なパズル
・ひらがなの練習
・数字の書き方練習
これらの活動を毎日コツコツ続けることで、「学ぶ」ことへの抵抗感をなくし、楽しみながら学習する姿勢を育てます。


我が家ではお風呂上がりのドライヤー時間を「夜のお勉強」として設定しましたよ。
わずか5分の継続が、将来の学習成功への第一歩となります。
4 論理的な思考力
「なぜ?」「どうして?」「◯◯だから△△だね」など、論理的に考え、自分の言葉で説明できる力を育てると、学習の理解が深まります。
論理的思考力があると、問題を解決する力が高まり、文章読解や算数の応用問題にも強くなります。OECD(経済協力開発機構)のPISA調査でも、論理的思考が学力向上に直結することが示されています。
- 遊びの中で「どうしてこの積み木は倒れたのかな?」などと理由を考えさせる
- 泣いたり怒ったりした時には、「◯◯だから△△だったんだね」と理由とセットで考えさせる
日常生活で「なぜ?」を問いかけ、「◯◯だから△△だ」と整理する習慣をつくることで、論理的思考力が育ち、小学校の学習理解がよりスムーズに進みます。
5 モリモリ食べる習慣


バランスの取れた食事と、おいしく食べる習慣は、子どもの成長と学習能力につながります。
それは、適切な栄養摂取は、脳の発達と認知機能の向上に重要な役割を果たすから。(国立成育医療研究センターの研究より)
我が家や担任する子ども達には「チビチビ食べるんじゃなくて、もりもり食べて元気になろうね!」といつも伝えます。
楽しく食べることを意識し、でも無理強いはせず、家族一緒に食事を楽しむことが大切です。そして、おいしく、バランスよく食べる習慣が、子どもの成長と学習を支えます。
入学準備についてよくある質問


小学校入学に向け、保護者の皆様から聞かれたことがある質問をまとめます。
通信教育やドリルは必要?
必ずしも必要ではありませんが、子どもの学習習慣をつけるためには有効です。また、幼少期における文字の読み書きや数字に強くなるには、とても強力な学びの相方になります。
ただし、子どもの興味やペースに合わせて無理なく取り組めるものを選ぶことが大切です。
我が子に実際に与えた幼児ポピーについては以下にくわしくまとめているので、ぜひご覧ください。
入学前にどんな本を読ませたらいい?
興味を持てる本なら何でもOKですが、物語・知識・生活習慣に関する本をバランスよく読むと良いでしょう。
国立青少年教育振興機構の調査によると、幼少期に多くの本に触れた子どもほど、読解力や語彙力が高まりやすいことがわかっています。特に物語の本は想像力を育み、知識の本は好奇心を刺激します。
例えば、虫が好きな子には『ざんねんないきもの事典』、お話が好きな子には『ぐりとぐら』、生活習慣を学びたいなら『おおきくなるっていうことは』など、興味に合った本を選ぶと楽しんで読めます。
子どもが好きな本を読むのが一番ですが、物語・知識・生活習慣の本をバランスよく取り入れることで、入学後の学びにも役立ちます。
子どもの学力を高める勉強法は?
日常生活の中で、遊びながら学ぶことが学力向上につながります。
学習指導要領にもあるように、小学校低学年では「体験的な学び」が重視されています。机の上だけでなく、生活の中で楽しく学ぶことで、知識が定着しやすくなります。
・買い物のときに「100円のりんごを2つ買ったらいくら?」と計算させてみる
・公園で見つけた植物や虫の名前を一緒に調べる
・外出中に見つけた文字を読み書きしてみる
子どもの学力を高めるには、机の上の勉強だけでなく、日常の体験を通じて「楽しく学ぶ」ことが大切です。以下の記事も参考にしてみてください!
友達関係で心配なことがあったらどうすればいい?
子どもの話をよく聞きつつ、すぐに親が介入せずに見守ることが大切です。
子ども同士のトラブルは成長の一部であり、自分で解決する力を育てる機会にもなります。教育心理学の研究でも、親がすぐに解決しようとするより、子どもが自分で考える時間を持つ方が、社会性の発達につながるとされています。
例えば、友達とおもちゃの取り合いをしたときに、すぐに大人が「貸してあげなさい」と言うより、「どうしたらお互い気持ちよく遊べるかな?」と考えさせる方が、次の場面でも自分で判断できるようになります。
友達関係の心配ごとは、まず子どもの話をよく聞き、すぐに解決しようとせずに見守ることが大切です。ただし、深刻な場合は学校や先生に相談しましょう。
5つの力を高めて小学校入学をばっちり迎えよう!


ここまで、現役小学校教師が我が子の小学校入学に向け、本気で家で取り組ませてきたことを紹介してきました。
- 1 ひらがな・カタカナ・数字の読み書きができるようになる
- 2 たし算・ひき算のイメージ作りができる
- 3 1日5分机に向かう習慣が定着している
- 4 論理的な思考力の素地ができる
- 5 モリモリ食べる習慣がある
小学校入学というスタートラインは同じでも、それまでの準備で大幅なフライングは十分に可能です。そしてその圧倒的な差は、子どもの学校生活の充実度や学びへの自信へと直結します。
ぜひ、それぞれのご家庭でできる限りの準備をし、4月の入学を万全で迎えられるようにしてみてくださいね。
〉【教師は言わない】小学生の成績を上げるために保護者ができることを現役教師が解説!