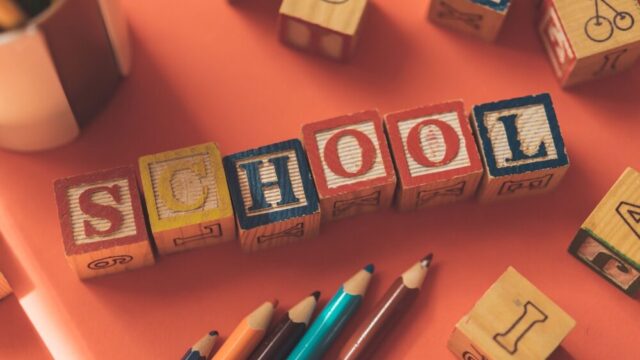- ・小学生の子どもがなかなか勉強しない…
- ・どうすれば勉強に対してやる気になるのかな…
- ・机に向かってもすぐに飽きてしまう…
小学生のうちに「勉強習慣」をつけられるかどうかで、その子の学力や成長のスピードは大きく変わります。
しかし「うちの子、勉強の習慣が全然つかない」と悩んでいる保護者はすごく多いです。子どもが自発的に勉強する習慣をつけるのは簡単ではありません。
そこでこの記事では、以下の内容を現役小学校教師の目線で詳しく解説します。
- 学力が高い小学生の共通点とは
- 子どもが勉強に集中できない理由
- 勉強習慣を身につけるために最も大切にすべきこと
- 学力を高める勉強方法7選
- 保護者の関わり方のポイント5選
- おすすめの学習ツール
私はこれまで、15年間で500人以上の小学生を指導し、その保護者にも数多くお話を伺ってきました。この記事では、現役の小学校教師である私が、実際に子どもたちに指導したり、保護者のお話から見つけた共通点を分かりやすく解説します。
ぜひ、親のストレスを減らしながら、子どもが楽しく学ぶコツを知って、お子さんの更なる成長につなげてくださいね。
学力が高い小学生の共通点とは

これまで小学1年生から6年生を担任し、学力が高い子から低い子までさまざまな子どもを指導してきました。その中で出会った「学力が高い子」には、共通点があります。
自分の考えを言語化できる
学力が高い小学生は、自分の考えを言葉で的確に表現できます。
自分の考えを言語化することで、思考が整理され、理解が深まります。また、相手に伝えることで、コミュニケーション能力も高まります。
圧倒的に学力が高かった小5のある女子は「先生、絶対にクラスに馴染みたくない子がいたらどう声かけるんですか」と私に聞いてきたことがあります。(採用試験の面接を思い出しましたね…笑)
このように、素朴な疑問を率直に聞ける子も言語化が得意な例の一つです。
自分の考えを言語化し、アウトプットできることは、学力向上に不可欠な能力といえます。
知的好奇心が高い
学力が高い小学生は、知らないことや不思議なことに興味を持ち、積極的に調べようとします。
知的好奇心の高さは、学習意欲を高め、探究心を養います。「分からない」ことを「分からない」ままにしない粘り強さにもつながりますね。
分からなかった問題に2時間かけて答えを出したある子は東大に合格しました。
知的好奇心は、学びを深めるための原動力となります。
情緒が安定している
学力が高い小学生は、感情のコントロールが上手で、落ち着いて学習に取り組めます。情緒が安定していることで、集中力が高まり、ストレスにも強いです。
一方、気持ちに乱れがある子の多くは、勉強に集中できないこともしばしば。まずはどう落ち着いて学習に向かおうか、ということを考えることになりますからね。
情緒の安定は、学習効率を高めるために重要な要素です。
規則正しい生活を送っている

学力が高い小学生は、早寝早起き、バランスの取れた食事、適度な運動など、規則正しい生活を送っています。
規則正しい生活は、心身の健康を保ち、学習に必要なエネルギーを蓄えます。
- 必ず10時までには寝て、朝は自分で起きている
- 動画やアニメは1時間までしか見ていない
- 朝ご飯は、必ずパンと牛乳と果物を食べる
学校の授業の1,2時間目は国語、算数が多いです。それは朝の内に、学力の基礎となる力を確実に高めたいと多くの教員が思うから。学力が高かった子はきまって、朝イチの授業から活動的です。
規則正しい生活は、学力を高める基盤となります。
自分で時間を管理できる
学力が高い小学生は、自己管理能力が高く、けじめをつけた生活が送れます。
時間を自分で管理できる力は、効率的な学習を促し、確実な学力アップにつながります。なぜなら、現代はゲームやテレビにスマホ、何なら学校から持ち帰るタブレットなど、時間を使おうと思えば際限なく時間を消費してしまう時代だから。
ある子の帰宅後の流れを聞くと、このように話してくれたことがあります。
- 宿題はもちろん、すぐに終わらせます
- それからはご飯までは絵を描いたり、自主勉強をしたり
- 19時から20時までの1時間だけはアニメを見ます
- 20時からは読書って決まってるので、今は◯◯を読んでます
親とルールを決めつつ、自分で時間をコントロールできる能力は、現代こそ必要不可欠といえるでしょう。
やるべきことに先に手をつけられる
学力が高い小学生は、面倒なことや苦手なことでも、後回しにせずに、先に片付けることができます。
この力は心理学では「実行機能」(executive function)の重要な要素として研究されています。

実行機能とは、目標達成のために必要な思考や行動をコントロールする能力のことです
優先順位をつけ、その通りに行動することで、時間内に効率よく課題をこなすことができます。「◯◯と△△をしないといけないけど、まだできていない…」と思わなくて良いので、情緒的な安定にもつながりますね。
先ほど例に出した子も「宿題はもちろん、すぐに終わらせます」と言っています。
優先順位をつけ、その通りに行動できる力は、目標達成のために重要な習慣です。
読書好き
学力が高い小学生は、様々なジャンルの本を読みます。
よく言われることですが、読書は、語彙力、読解力、思考力を高め、知識を広げてくれますね。
圧倒的に学力が高かった子で読書が嫌いな子は本当に一人もいませんでしたね。というより全員読書が楽しいと思える子ばかりです。

うちの子、なかなか本を読まなくて…
そんな場合は読み聞かせをしたり、親子で交互に本を読んだりするところからスタートしましょう。(子どもを読書好きにさせることについて解説した記事も公開予定です)
読書は、学習の土台となる力を育みます。
子どもが勉強に集中できない理由

子どもが勉強に集中できない理由は一つではありません。様々な要因が複雑に絡み合っているため、一概に「〇〇が悪い」と決めつけるのは禁物です。
これまでより丁寧に指導しても、なかなか学力が上がらなかった子どもの特徴や家庭の共通点をまとめました。
誘惑が多い環境になっている
家には、テレビ、ゲーム、スマホ、漫画など、子どもの興味を引くものがたくさんあります。学校から持ち帰るタブレットもその要因の一つといっていいでしょう。
これらは、子どもが勉強に集中しようとしても、ついそちらに気を取られてしまう原因になります。勉強机の横にゲーム機があると、勉強中にゲームのことが気になってしまい、集中できなくなることがあります。

親だってついスマホを手に取ってショート動画を…ですよね?
家庭環境における誘惑の多さは、子どもの集中力を著しく低下させる原因の一つと言えます。
勉強環境が整っていない
勉強環境が整っていないのは子どもが勉強に集中できない原因となります。これは人の集中力と環境には密接な関係があるから。
整理整頓されていない環境や、騒がしい環境は、子どもの集中力を妨げ、勉強が苦手となる要因となります。
勉強は「嫌なもの」と思い込んでいる
勉強に対して「つまらない」「難しい」「嫌いだ」という気持ちがあると、集中力が続きません。
実際、勉強が嫌いな子は、勉強時間や宿題をしないといけないと思うと、憂鬱な気持ちになったり、逃げ出したくなったりすることがあります。
勉強が苦手なある子は「やらないといけないと思うと、嫌でゲームや動画を見てしまう」と言っていました。

大人でも嫌だと思うこと、苦手なことからは逃げたくもなりますもんね…
勉強に対するネガティブな感情は、子どもの集中力を低下させる大きな要因となります。
保護者から必要以上に介入される
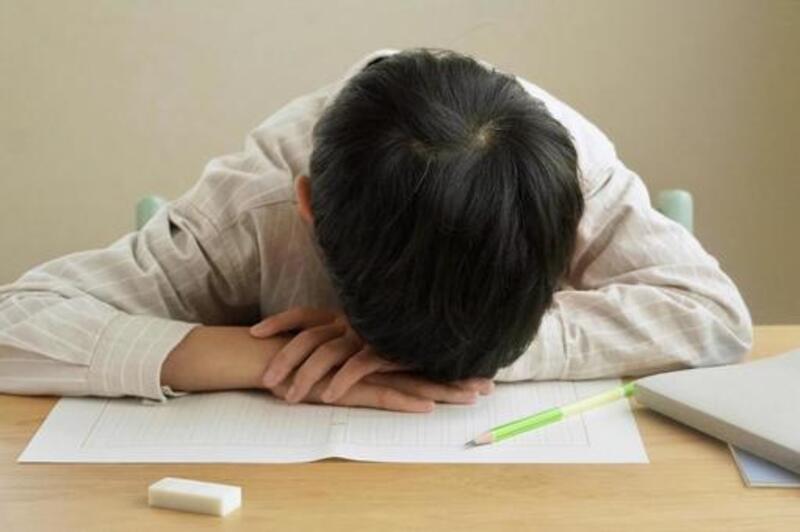
保護者から必要以上に介入されることも勉強を嫌いになる原因となります。
これは大人も経験的に分かることでもあるのではないでしょうか。

「言われたら逆にやりたくなくなってしまう」そんな経験ありますよね?
これは心理学の分野で「ブーメラン効果」といわれています。相手を一生懸命に説得すればするほど、逆に反発が起こり、望んでいた行動とは反対の行動を引き起こしてしまう現象ですね。
保護者の過度な介入は、子どもの自律性を阻害し、学習意欲を低下させる原因となります。
学力を高めるための勉強方法7選

子どもの学力を高めるには、ただ勉強時間を増やすだけでは不十分です。大切なのは、効率よく学べる環境を整え、正しい方法で集中して学習に取り組むこと。
ぜひ、お子さんに合った方法を見つけてみてください。
①目標と計画を立てる
勉強を始める前に、「何を、いつまでに、どうやって達成したいか」 を決めると、迷子にならずにゴールまでたどり着けます。
目標は、「算数のテストで80点以上取る!」 「漢字テストで100点を目指す!」みたいに、頑張れば達成できるくらいの具体的なものが良いですね。
そして、その目標を達成するための、具体的な行動計画をセットで立てましょう。目標だけ決めて行動に繋がらないと、子どもが自信をなくす原因にもなってしまいます。
- 毎日、算数の問題を10問解く
- 宿題の後、ドリルを1ページ進める
- お風呂の後は必ず10分読書する
計画を立てたら、それを実行するだけ。もし計画通りに進まなくても、途中で修正すれば大丈夫。大切なのは、「目標を達成する!」 という気持ちを持ち、そのための行動をコツコツ続けることなんです。
②勉強する時間をルーティン化する
毎日、同じ時間に勉強する習慣をつけることは、毎日同じ時間に学校に行くのと同じ。学校に行くのが当たり前のように、勉強するのも当たり前です。
「小さい頃から「勉強はあなたの仕事」と伝える」(https://www.himawari-child.com/knowledge/9.html)
このように、勉強は「がんばってやるもの、努力するもの」ではなく「当たり前にするもの」という意識づけをすることが大切です。
- 帰ったら一番に宿題を終わらせる
- ご飯を食べたら勉強する
- お風呂に入る前に15分だけ勉強する
このように、自分の生活の中に勉強する時間を組み込めると良いですね。
ルーティン化することで、「やらなきゃ」 という気持ちが減って、自然と勉強できるようになりますよ。

ちなみに我が家の年長の娘は、お風呂上がりに髪を乾かしながらドリルを1ページ進めるのが日課になっています!
③勉強する場所を固定化する
勉強する場所を固定化する方法も、勉強の習慣化には有効です。
そこに行くだけで「よし、やろう!」 という気持ちになれるんです。まるで、スポーツ選手がユニフォームに着替えるとやる気になってくるのと同じですね。
- 自分の部屋の机で勉強する
- リビングのテーブルで勉強する
- カウンターで勉強する
場所はどこでも良いので、集中できる場所を決めましょう。
勉強する時間と場所をルーティン化し、勉強を生活の一部に組み入れることができれば、勉強の習慣化はできてきますね。
④予習と復習を取り入れる
勉強内容は「予習」と「復習」を基本にすると良いでしょう。
予習は、「明日の授業の予行練習」 みたいなもの。事前に教科書を読んでおくことで、授業の内容が理解しやすくなります。
復習は、「今日習ったことの確認テスト」 みたいなもの。授業で習ったことをその日のうちに復習することで、記憶に残りやすくなります。
予習と復習は、セットで行うと、さらに効果的。予習で疑問に思ったことを授業で解決し、復習で知識を定着させるイメージですね。
小学校低学年から、予習と復習で「わかった!」「できる!」という思いを積み重ねられると、勉強に対する自信がついてきます。この気持ちが何より大事。
学校の勉強の「予習」と「復習」をセットにして勉強習慣を身につけられるようにしてあげてくださいね。
≫【学校任せは危険!】家庭でできる学力アップのための具体的な3ステップを公開
⑤アウトプットさせる
勉強した内容をアウトプットするのを日常的に取り入れるのも効果抜群です。
アメリカ国立訓練研究所が提唱した「ラーニングピラミッド」が有名で、自分の言葉で誰かに教えたり、説明することが、最も学習定着率が高かったという研究結果が出ています。つまり、人に説明したり、書いたりしてアウトプットする「学んだこと発表会」 をしようということ。
友達と問題を出し合ったり、家族に今日習ったことをクイズにして出したりするのも良いですね。
もし誰もいなかったら、ノートにまとめたり、絵を描いたりするのもOK。子どもの年齢やレベルに合わせた子どもなりのアウトプットにチャレンジしてみましょう。
⑥計算や漢字をゲーム感覚で取り組む
計算練習や漢字を覚える勉強をゲーム感覚で「楽しい時間」に変えることで、子どもは自然と机に向かうようになります。
ゲーム感覚の学習が効果的な理由は、子どもの脳が「遊び」を通じて最も効率よく学習するように作られているためです。ゲーム要素を取り入れることで、ドーパミンという脳内物質が分泌され、やる気と集中力が高まります。また、「遊び」の中で繰り返し学習することで、自然と記憶が定着しやすくなるという効果もあります。
- 計算カードを使って「神経衰弱」をする
- 漢字の書き順を体で表現する「漢字体操」
- 間違い探しのように漢字の部首を探す
- タイムアタックで計算ドリルに挑戦する
- 家族で漢字しりとりを楽しむ
このように「勉強」を「遊び」に変えることで、子どもは苦手意識を持つことなく基礎学力を身につけることができます。まずは家庭で楽しく始められる方法から、少しずつ試してみましょう。
⑦学習の振り返りをする
その日の学習内容を振り返る習慣をつけることで、子どもの理解力と学習効果が大きく向上します。
振り返りが効果的な理由は、脳の記憶定着の仕組みにあります。学んだ内容を自分の言葉で整理し直すことで、短期記憶が長期記憶に変換されやすくなります。また、自分の理解度を確認することで、苦手分野を早期に発見し、効率的な学習計画を立てることにもつながります。

苦手の発見、克服は高学年になるにつれて求められる力ですね!
- 学習ノートに「わかったこと」「まだむずかしいこと」を書く
- 家族に今日習ったことを教える時間を作る
- カレンダーに学習内容と感想を短く記録する
- 週末に1週間の復習をする
わずか5分の振り返りでも、学習効果は格段に高まります。まずは子どもと一緒に、その日の学習で印象に残ったことを話し合うところから始めてみましょう。この小さな習慣が、確実な学力向上につながっていきます。
保護者の関わり方のポイント7選

小学生が勉強に集中して取り組み、学習習慣を身につけるためには、保護者の関わりは欠かせません。小学生が勉強できるようになるために、今日から保護者ができることを紹介します。
子どもが学ぶ場にいる
子どもは親の存在を感じることで安心感を得られ、集中力が高まります。また、困ったときにすぐに質問できる環境があることで、学習のつまずきを早期に解決できます。
親が近くにいることで、子どもは「勉強」を特別なことではなく、日常の一部として受け入れやすくなります。
- リビングのテーブルで、親は読書や家計簿をつけながら見守る
- 子どもの机の近くで、親も自分の仕事をする
- 同じ空間で、兄弟が一緒に学習する時間を作る
子どもの学習環境に寄り添うことで、自然と学習習慣が形作られていきます。決して監視ではなく、さりげない見守りを心がけましょう。
親も一緒に学習する
親が学ぶ姿を見せることで、子どもの学習意欲が高まり、家庭全体に学びの雰囲気が生まれます。
子どもは親の行動を見て育ちます。親自身が学ぶことを楽しむ姿を見せることで、学習に対する前向きな態度が自然と身についていきます。また、親子で学び合うことで、コミュニケーションも深まります。
- 親も新しい言語や趣味を学ぶ
- 子どもの教科書を一緒に読んで感想を話し合う
- 親子で図書館に行き、それぞれの本を選ぶ
家族で学び合う環境を作ることで、子どもの学習意欲は自然と高まっていきます。まずは親自身が学ぶ楽しさを実践してみましょう。
学習内容に関心を持つ

子どもの学習内容に関心を示すことで、学びの意欲が引き出され、理解が深まります。
子どもは親が関心を持つことで、学習の意義を実感できます。また、学校での学びと日常生活のつながりを意識することで、より深い理解が促されます。教科の内容を一緒に考えることで、親子の対話も増えていきますね。
「今日は何を習ったの?「前、勉強していたことと関係があるね」などと声をかけ、学習に関心があることを伝えてあげましょう。
子どもの学びに寄り添うことで、学習意欲は自然と高まっていきます。まずは、その日の学習内容について、短い会話から始めてみましょう。
いつでも話しやすい雰囲気をつくる
子どもが気軽に質問や相談ができる環境があることで、学習の壁を早期に乗り越えられます。
子どもは「わからない」と言いづらい気持ちを抱えがち。だからこそ、親が受容的な態度を示すことで、失敗を恐れず、積極的に学ぶ姿勢が育ちます。
また、学習の悩みを共有することで、適切なサポートのタイミングを逃しません。

学校でも「分からないから教えてください」と言える子は伸びますね!
- 「わからなくて当たり前」と伝える
- 質問されたらすぐに答えを教えず、一緒に考える
- 学習以外の話題でも日常的に会話を楽しむ
オープンな対話ができる関係を築くことで、子どもは安心して学習に取り組めます。まずは、日々の何気ない会話を大切にしましょう。
「ご褒美」より「成長の実感」を大切にする
テストの点数や結果だけでなく、努力のプロセスに目を向け、子どもが自身の成長を実感できるようにすることで、持続的な学習意欲が育まれます。
外的な報酬に頼ると、学習意欲が一時的なものになりがちです。子ども自身が「できるようになった」という実感を持つことで、内発的な学習動機が強まり、自主的な学習習慣が身につきます。
- 以前できなかったことができるようになった場面を具体的に伝える
- 努力の過程を認める言葉がけをする
- 小さな進歩も見逃さず、共に喜ぶ

「テストで◯点取ったら…」「通知簿で3が◯個なら…」と、結果やご褒美に目がいってしまわないようにしましょう!
子どもの成長に寄り添い、それを言葉にして伝えることで、学習意欲は持続的に高まっていきます。日々の小さな進歩に目を向けましょう。
子どもの自由を確保する
学習時間や方法について、ある程度の選択権を子どもに委ねることで、自主性と責任感が育ちます。

学力が高い子はみんな、勉強以外の時間にはゲームやアニメなどしっかり自由を楽しんでいますよ!
過度な管理や強制は、かえって学習意欲を低下させる原因となります。適度な自由があることで、自己管理能力が育ち、主体的な学習態度が形成されます。また、勉強をがんばる時間を確保しているからこそ、それ以外の時間はしっかり遊べるようにしてあげたいですね。
子どもの自主性を尊重しながら、見守る姿勢を持つことで、確実な学習習慣が身についていきます。また、まずは小さな選択から、任せてみましょう。
がんばりを評価する
結果だけでなく、努力のプロセスを具体的に認めることで、子どもの学習意欲が持続的に高まります。
子どもは、自分の努力が認められることで、学習に対する自信と意欲を得ます。また、具体的な評価を受けることで、効果的な学習方法を理解し、自己改善することができます。
- 粘り強く取り組む姿勢を言葉で伝える
- 工夫して学習している点を具体的に褒める
- 失敗しても諦めずに挑戦する態度を認める
- 結果ではなく素敵だと思うところを伝える
子どものがんばりに寄り添い、具体的な言葉で伝えることで、学習意欲は着実に育っていきます。日々の努力のプロセスに目を向けましょう。
≫【教師は言わない】小学生の成績を上げるために保護者ができることを現役教師が解説!
おすすめの学習ツール

小学生が学力を高められるコスパ最強のおすすめの学習ツールを紹介します。多くのドリルや問題集、知育アプリなどのサービスがありますが、シンプルに考えて大丈夫です。
結論は「学校の宿題」+「スタディサプリ」です。詳しく解説します。
学校の宿題
学校の宿題は、学習内容の定着に欠かせない、最も身近で効果的な学習ツールです。また、学習習慣の定着としても最適です。
現在、多くの学校、学級で宿題が出されていることでしょう。私自身も毎日、決まった宿題を子どもに出しています。宿題は、授業で学んだ内容の定着として出すことがほとんど。
つまり、宿題に取り組むことは、学校で学んだ知識をしっかりと定着させることにつながります。また、毎日出される宿題に取り組むことで、学習習慣の定着につながるというメリットもあります。
一方、宿題だけでは、思考力アップや成績向上につなげることは難しいです。その理由は、教師は確実にできる内容のものしか宿題には出さないから。(小学生の成績を上げることについて赤裸々に告白した記事については以下の記事を参考にしてください)
宿題は学力の基礎となる知識や技能、そして学習習慣の定着が目的だと理解してください。
スタディサプリ
スタディサプリは、多様な学習コンテンツと分かりやすい解説で、子どもの学習意欲と学力を高め、勉強の理解を深めるための強力でありながら、コスパ最強の学習サポートツールです。
スタディサプリは、教科書の内容に沿った授業動画や豊富な問題、ゲーム感覚で学べるドリルなど、様々な学習コンテンツを提供しています。また、各教科のプロ講師による分かりやすい解説は、子どもたちの理解を深め、「分からない」を「分かった!」に変えることができます。

実際、日々子どもに指導している私自身もスタサプ講師陣の教え方が大いに参考になっています
スタディサプリは、「家庭教師」 兼 「優秀な参考書」。分からないことがあれば、いつでもどこでもプロの先生に教えてもらうことができ、様々なレベルの問題に挑戦することで、自分の力を試すこともできます。
スタディサプリは、子どもの学習意欲を高め、理解を深めるための、強力な学習サポートツールと言えるでしょう。
≫スタディサプリは小学校低学年にもおすすめ!【無料で14日間お試しつき】
≫【2025年】小学生向け通信教育おすすめランキング!厳選5つを小学校教師が解説!
【まとめ】学習習慣を身につけ、学力アップにつなげよう!

ここまで、小学生が学習習慣を身につけるための方法や保護者の関わり方について、具体的に解説してきました。
- 学力が高い小学生は「知的好奇心が強い」「情緒が安定している」などの共通点がある
- 子どもが勉強に集中できない原因は「環境」や「思い込み」「保護者の関わり」にある
- 学力を高めるための勉強方法は以下の7つ。
①目標と計画を立てる
②勉強する時間のルーティン化する
③勉強する場所を固定化する
④予習と復習を取り入れる
⑤アウトプットさせる
⑥計算や漢字をゲーム感覚で取り組む
⑦学習の振り返りをする - 保護者は「一緒に勉強する」「話やすい雰囲気をつくる」「自由を確保する」など、サポートを行う
- 「学校の宿題」と「スタディサプリ」で勉強習慣の定着と学力をアップさせる
これまで500人以上の小学生とその保護者と接してきました。その中で、私自身が見て、そして話して得た知識と経験をまとめました。
この記事が保護者の皆様の行動につながる一助に、そしてさらにお子様の勉強習慣の定着と学力アップにつながれば何より嬉しいです。