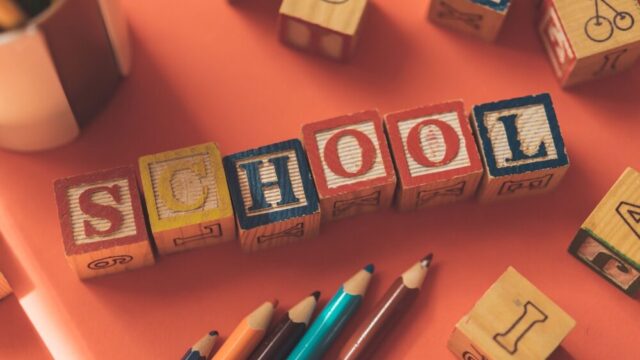「うちの子…授業中に最後まで座ってられるかな」
「新しい人間関係や友だちづくりがうまくいくか心配…」
「小学校に行きたくないと言い出さないか不安…」
幼稚園や保育園でのびのびと過ごしていた子どもたちが、小学校に入学すると突然直面する「小1プロブレム」。小学校入学を控えたお子さんを持つ保護者の皆さんの中には、小1プロブレムへの不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では以下の内容を、現役小学校教師がありのままに解説していきます。
- 小1プロブレムの具体例と問題点
- 小1プロブレムが起こる原因
- 小1プロブレムを未然に防ぐための具体的な解決策
小学校入学を控えるお子様を持つ保護者はもちろん、現在小学生のお子様を持つ保護者にも参考になる内容です。ぜひこの記事を参考に、お子様の有意義な小学校生活をスタートさせてください。
入学後に陥る小1プロブレムとは

小1プロブレムとは、幼稚園や保育園から小学校に上がった子どもたちが、新しい環境にうまく適応できず、精神的に不安定な状態が続くことで起こる問題を指します。現役小学校教師がこれまで実際に見てきたケースをあげて説明していきます。
小1プロブレムの具体例5選
小1プロブレムは入学後の数週間から数ヶ月の間に起こります。これまで多く見てきたのは以下のような姿です。
- 登校を渋る
- 感情のコントロールができない
- 話を聞かない
- 授業中に立ち歩く
- 自分勝手な行動をする
それぞれ詳しく解説していきます。
登校を渋る
朝、家で登校するのを渋るようになります。学校に行きたくないという理由は「勉強が難しい」「先生が怖い」「行きたくない」など様々です。
保護者と一緒に登校する子や不安ながらも登校してくる子は、学校に来れば元気に過ごせる子が多いことも。ですが、中には保護者の車から泣いて降りようとしない子や暴れまわって手がつけられない状態になってしまう子もいます。
小学校入学後に登校できなくなり、そのまま何年も不登校になってしまった子もいます。
感情のコントロールができない
感情のコントロールができなくなる子も多く見られます。ほんの小さなトラブルで泣いたり、怒ったりする子もいれば、中には理由もなく涙が止まらない子や怒ってばかりの子もいます。また、自分の気持ちがうまく伝えられず友達と何度もトラブルになってしまう子も。
一方、授業は決められた時刻通りに確実に進んでいくので、感情のコントロールができない子はどんどんストレスを抱えていくことになってしまうのが現状です。
話を聞かない
話を聞かない(聞けない)子も。小学校の授業という形態上、「先生の話を聞く」のを大前提としています。しかし、話を聞けない子は、周りの子の動きから遅れたり、学習が全く理解できなかったりという状況に陥っていきます。
そうすると、どんどん「勉強がわからない」「授業がおもしろくない」という悪循環に。次第に登校を渋るようになるというケースも数多く見てきました。

この悪循環に陥ると、子どもも先生も「シンドい」です。本当に…
授業中に立ち歩く
授業中にウロウロと立ち歩くようになる子もいます。授業に集中できず、手遊びやキョロキョロするようになり、次第に教室内を、さらには教室の外にもウロウロと立ち歩くようになります。
教師はクラス全員に学習内容を理解させようと授業をしていますよね。(もう日々必死です…)なので、立ち歩く子には、強い口調での指摘をするようになっていくこともしばしば。そうなってくると「先生が怖い」「授業がいやだ」と、どんどんエスカレートして、授業妨害や逃避をするようになってしまうのです。
自分勝手な行動をする
自分勝手な行動で周りを困らせる存在になってしまうこともあります。授業のルールを守らない、教師の言うことを聞かない、友達に迷惑をかける、時間を守らないなど、周りに合わせたり、教師に言われたことを聞いたりせず、どんどん自分勝手な行動をとるようになります。
小1プロブレムの最大の問題点は「自信の喪失」
小1プロブレムの最大の問題点は、子どもたちが自信を失うことであり、その後の学校生活への意欲や成長に様々な影響を及ぼすことにあります。なぜなら、今の学校教育は教室で落ち着いて学習し、テストで一定の点数を取ることが大前提になっているからです。
- 感情が乱れ、落ち着いて生活できない
- 話を聞けず、学習がわからない
- 学校に行けなくなる

小1プロブレムに陥った子たちが自信をもって生活できるはずありませんよね。
また「学校には行くもんだ」「勉強はするもんだ」という「従来の教育観」での子どもへの接し方も、子どもの自信を奪います。口にはしなくとも、「そんなこと当たり前」「そんなことができないの」という大人の気持ちは子どもには伝わるものです。
これまで実際、小1プロブレムに直面した子がそれ以降、何年にもわたって自信を失い、できるはずだった成長をできないままに大きくなった姿を見てきました。
このように、小1プロブレムは子どもの自信を失わせ、その後の成長を奪うことにつながってしまうのです。
小1プロブレムが起こる原因とは

小学校に入学した子どもが小1プロブレムになる原因はいくつかあります。その多くは小学校入学まで過ごした環境との大きな違いによるものです。
生活リズムの大きな変化
小学校入学による生活リズムの変化は、子どもにとって大きなストレス要因となります。
幼稚園や保育園とは異なる早起きや長時間の授業、宿題など、生活習慣が大きく変わるため、適応に時間がかかることが多いです。新入生の約35%が生活リズムの変化に戸惑いを感じているという調査もあるようです。
例えば、幼稚園や保育園時代は、「朝の準備ができたら登園する」ということも多いですよね。ですが、小学校では集合時刻や授業の開始時刻、食べ終わらなければならない給食の時刻など、「ねばらならない時刻」がしっかりと決められています。
このように、小学校入学による生活リズムの大きな変化は、子どもにとって大きなストレスの要因となります。
人間関係の変化
新しい友だちや先生との関係を築くことは、子どもにとって大きな挑戦です。
実際、小学校では、保育園や幼稚園とは異なる新しい集団に適応する必要があります。新しい環境の中で、新しい関係構築にストレスを感じる子どもは多く、結果的に小1プロブレムの原因となることがあります。
大人でも、初めての職場に入ったときには大きなストレスを感じますよね。名前も知らない同僚と接しながら、今までと大きく違う生活リズムの中でうまく順応するのは難しく、大きなストレスを感じるはず。
小学校入学後の人間関係の大きな変化に順応できず、小1プロブレムにつながるケースも少なくありません。
立場の大きな変化
「幼稚園児、保育園児」から「小学生」という新しい立場への変化は、子どもに責任感とプレッシャーを与えます。
数日前までは「頼もしいリーダー!」「お兄さん!お姉さん!」ともてはやされていた子どもたちは、突然「小学生」としての役割を期待されることが多く、その期待に応えようとする中でストレスを感じることがあります。
「もう小学生なんだから…」
「小学生になると…」
「小学生なら…」
そんな突然の「小学生プレッシャー」を感じつつ、小学校では「何も知らない1年生」として、教師や上級生から必要以上に丁寧に接せられる。
このように、突然の大きな変化から小1プロブレムにつながることもあります。

つい数日前までとのギャップに戸惑うのは当然ですよね…
「指導」に対する戸惑い
保育園や幼稚園の「保育」と異なり、小学校での「指導」は、子どもに戸惑いを与えることがあります。
・「〜しなさい」という教師からの具体的な指示
・「〜しなければなりません」という決められたルール
・「〜できましたね」という教師からの一方的な評価
約30%の子どもが「指導が怖い」と感じた経験があると、日本小児学会の調査での報告も。
幼稚園や保育園での先生の接し方と、小学校教師の指導の接し方の違いから、子どもには大きな圧力として感じられることもあるのが実際です。
「自由」が多いに認められていた矢先に、突然「ルール通りにやりなさい」と厳しく言われるのですから、楽しさよりも緊張感が勝ってしまうのも当然。「きちんと指導する」という小学校教師の仕事が、小1プロブレムにつながっている悲しい現実です。
「ルールの多さ」に対する戸惑い
学校のルールがあまりにも多く、ルールを守る難しさが小1プロブレムの原因になることもあります。
・授業を受けるときは、姿勢を良くして、机の上には…
・チャイムがなったら、着席し、次の時間の準備を…
・給食を配るときは…、配膳を待つ人は…
・廊下では右側を歩いて…
・筆箱の中は…、持って良いものは…、タブレットは必ず…
・家に帰ったら一番に…
あげればきりがないほど、学校には守るべきルールがありますよね。
自由にのびのびと過ごしてきた生活から一変。ルールと束縛に苦労する小学1年生が出てくるのも、ある意味当然です。
家庭でできる小1プロブレムへの完璧な対策7選


小1プロブレムってなるべくしてなってしまうのか…
そんな風に絶望しないでください。実際に小学校で勤務する立場から、小1プロブレムへの対策をお伝えします。
色々な子どもがいますから、「これをしていれば必ず小1プロブレムにならない!」とは断言できません。ですが、「小1プロブレムになる可能性をぐーんと下げられる」とは断言できます。それぞれ詳しく解説します。
小学生のお兄さん、お姉さんとのつながりをつくる
小学生の先輩たちと関わりをつくっておくことは、1年生の学校生活への不安を軽減できます。
それは年上の子どもと関わることで、学校生活の流れを自然に学べるからです。また、小学校入学後、顔馴染みの上級生がいるのは、想像以上に安心感を与えてくれるものです。
実際、小学校に入学したばかりで緊張していた子も、兄弟や近所の上級生が同じ学校に通っていることで安心感を感じ、小学校へのハードルが下がるケースはそこら中で見られるものです。
兄弟や近所の年上の子、もしくは友達の兄妹や習い事の先輩など、つながりがつくれそうな場合は、意識的につながっておくようにしましょう。
同級生の友達をつくる
同級生の友達を作ることは、学校生活を楽しくし、子どもの安心感を高めるために重要です。
友達がいることで、学校での楽しさが増し、孤立感を減らすことにもつながります。ある心理学の研究によると、友達がいる子どもは学校生活でのストレスが大幅に軽減されるという報告もあります。
実際に大人でも、知らない場所で顔馴染みの姿が見られると、ホッと安心しますよね。
同級生の友達ということは、多くは保育園や幼稚園でできた友達でしょう。夕方や休日に遊んで、仲を深めておくことで、小学校入学後のお互いの支えになり、小1プロブレムの予防につながること間違いなしです。

やはり、人とのつながりによる安心感は大きいですね!
学習習慣をつくる
毎日の学習習慣は、小学校生活をスムーズに始める鍵となります。
家庭での学習習慣があると、学校の授業に対する理解度が高まりやすくなります。また、授業へのハードルも一段と低いものになります。学習習慣とは具体的に以下のようなものです。
- 鉛筆を使って文字や絵を書く
- 落ち着いて、一人で読書する
- 席について問題やノートに向かう
1日5時間もの授業が当たり前に始まる小学校生活。小学校入学までに落ち着いて机に向かう習慣がある子どもは、間違いなく強いです。何より、学習に対する自信を持っています。
市販のドリルや通信教育を活用して、無理のない範囲で学習習慣を身につけておきましょう。具体的には毎日、5分間机に向かう学習習慣づくりを目指すと良いでしょう。小学校入学までにおすすめの家庭学習についてまとめた記事も参考にしてください。
1年生の学習を先取りする
学校で学ぶ内容を少しだけでも事前に触れておくと、授業がスムーズに理解できます。
先取り学習をしておくことで、授業内容に対する理解は一気にスムーズになります。これは、子どもたちが授業中に自信を持って取り組むことにつながります。


1年生の学習を先に勉強しておくと、授業がつまらなくなるのでは?
そんな意見もありますが、それはもっと学年が大きくなってからのこと。1年生の学習は「できて当たり前」の内容ばかりです。
だからこそ、「できて当たり前」にしておくことが絶対に必要です。「できて当たり前」ができない挫折や苦労は、小1プロブレムに直結します。具体的には小学校入学までに
- ひらがなが書ける
- カタカナが読める
- くり上がり、くり下がりのないたし算、ひき算ができる
などができていれば十分でしょう。
以下の記事でくわしく解説している幼児ポピーなら、月1500円で1年生の先取り学習はほぼバッチリです。
時間を守る練習をする
時間を守る練習は、学校生活のリズムに適応する助けとなります。
学校では時間割があり、時間管理が求められます。幼稚園や保育園との大きな違いの一つといえます。時間を守る習慣を身につけることで、授業や休み時間の区別がはっきりし、学校生活へのハードルを下げられます。
- 生活に時計を読む習慣を取り入れる
- 朝の準備時間を決める
- 終わりの時間を意識して行動する
このように生活の中で時刻を守る練習をしておくことで、小学校に入学してからのギャップを和らげることができますよ。
自分の思いを話す力をつける
自分の気持ちを伝えられる力を高めておくことも、小1プロブレムを防ぐのに効果が高いです。なぜなら、自分の気持ちを伝えられる力は友達や先生との良好な関係を築く基盤になるからです。
小学校という特殊な環境では、ドキドキしたり、不安になったり、どうして良いかわからなくなったりすることだらけです。そんな時に
・自分で気持ちを伝えてすっきりできる
・気持ちを察してもらってすっきりできる
この違いはとてつもなく大きいです。特に言えるようにしておくと良い言葉は「分からないので教えてください」です。
小学校入学前から、「分からないから教えて」を言える習慣作りをしてあげてください。そして、遠慮なく「分からないから教えて」を伝えて良いんだと教えてあげてください。
結果ではなく過程を褒め、自信をつける
子どもが自分に自信を持てているかどうかは、小1プロブレムにも多いに関係します。
理由は小学校入学後に「指導と評価」が繰り返される環境に変わるから。つまり「できる」「できない」がより顕著になるということです。
よく「自己肯定感」と表現されるのにも似ていますね。自己肯定感を高め、自信をつけるために大切なのが「過程をほめること」です。努力を褒めると、結果が出なくても挑戦する意欲が育ちます。また、子どもが自分自身の成長に気づき、自信を持つことにもつながります。
普段からの声かけを結果ではなく、過程を評価するように心がけてあげてくださいね。
- 「上手にできたね」(結果)ではなく「がんばってやったんだね」(過程)
- 「間違えたね」(結果)ではなく「よく考えたね」(過程)
- 「◯位になれたね」(結果)ではなく「たくさん練習できたね」(過程)
小学校という特殊な環境になっても、自分に自信を持って、何事にも前向きな姿勢を持てるようになりますよ。
小1プロブレムを理解し、楽しい小学校生活をスタートさせよう


ここまで小1プロブレムの具体例と問題点、小1プロブレムが起こる原因とその対策を解説してきました。
- 小1プロブレムの最大の問題は子どもが自信を失うこと
- 小1プロブレムは「登校を渋る」「感情のコントロールができない」「話を聞かない」「授業中に立ち歩く」「自分勝手な行動をする」などの行動となって現れる
- 小1プロブレムが起こる原因は「生活リズムの変化」「人間関係の変化」「立場の変化」「「指導」に対する戸惑い」「「ルールの多さ」に対する戸惑い」であることが多い
- 小1プロブレム対策として「小学生のお兄さん、お姉さんとのつながりを作る」「同級生の友達を作る」「学習習慣を作る」「1年生の学習を先取りする」「時間を守る練習をする」「自分の思いを話す力をつける」「結果ではなく過程を褒め、自信をつける」
幼稚園や保育園とは大きく環境が変化する小学校生活。子どもにとって大きなストレスになるのは間違いありません。そこに小1プロブレムが起こると、保護者にとってもストレスになる時間を過ごすことになります。
できる限りの予防をしつつも、「なるようにしかならない」と割り切りながら、親子で楽しい小学校生活を送っていただけることを願っています。他の記事もぜひ参考にしてみてくださいね!